高貴だった日本女性 ~ 子供の想い出を胸に生きる
阿弥陀寺の比丘尼 小泉八雲『心』より
 ←はじめにクリックお願いします m(__)m
←はじめにクリックお願いします m(__)m(2020.10.27)
【あみだ寺の比丘尼(びくに)】
おとよの夫は、おとよのまたいとこで、たがいに思い思われた中で婿にきた男である。その夫が、領主に呼ばれて京へのぼった時、おとよは、ことさらさきざきのことなど案じもしなかった。おとよは、ただ心ぼそいと思った。が、両親もそばにいることだったし、それに、このことはじぶんではおくびにも出さなかったが、おとよには、生みの親よりもはるかに愛着の深い、小さなせがれがあったのである。のみならず、おとよは、ふだん自分のする用がたくさんある体だった。いろいろ家の切りもりにも当たらなければならなかったし、絹や木綿の機を織る仕事もいっぱいある身だった。
おとよは、日に一度ずつ、いつも決まった時刻に、留守の夫のために、夫がふだん寝起きしていたなじみのふかい部屋へ、きれいな塗りもの膳に手落ちなく整えた、蔭膳をすえた。蔭膳というのは、先祖代々の霊や神棚にそなえる、お供え膳のまねことのようなものである。このかげ膳は、いつも必ず、座敷の東側に供えられた。そして膳の前には、型のように、夫の敷きなれた座ぶとんが敷かれた。膳を東向きにするのは、夫が東の方へ旅立ったからである。おとよは、膳のものを下げる前に、いつも忘れずに、小さな汁椀のふたをとって、そのふたの内側に湯気がたまっているかどうかをあらためて見た。供えた汁椀のふたの内がわに湯気がたまっていれば、旅に出ている人は無事息災だというのである。湯気がたまっていないと、その人は死んでいるのである。つまりそれは、その人のたましいが食べ物を求めに帰ってきたというしるしなのである。おとよは、来る日も来る日も、椀のふたに、湯気のしずくが大きな玉になっているのを見た。
子供は、おとよが常住(じょうじゅう:永遠不変なこと)のよろこびであった。まだやっと三つであったが、この子は、よく神様でなければほんとの答えは御存知ないようなことばかり、好んで聞きたがった。子供が遊びたいといえば、おとよはいつもしかけた仕事の手をおいて、いっしょに相手になって遊んでやった。子供が眠くなると、おとよは、きまっておもしろい話をしてきかせたり、余人にはとてもわからないようなことを尋ねる子供の問いに、いちいち克明に答えてやったりした。夕方になると、仏壇や神棚に、小さなお灯明があがる。すると、おとよは、片言まじりに、子供に父親の無事を祈ることを教えてやるのである。そんなことをしているうちに、やがて、子供が床に寝つく。するとおとよは枕元へ仕事をもってきて、がんぜない子供の寝顔を、いつまでも、いつまでも、見守って飽きないのである。どうかすると、眠っている子供が、夢の中でにっこり笑ったりすることがある。それを見ると、おとよは、これはきっと観音さまが夢の中で、坊やといっしょに遊んでいらっしゃるのだとこころえて、「世上一切の祈願の音声(おんじょう)を常住に観じ給う」あの処女菩薩に向かって、さっそく口の中でお経の文句をとなえるのだった。
春になって、毎日、うち晴れた天気が続くようになると、おとよは、よく子供を負ぶっては、ダケヤマ(嵩山)へ登った。こういう遊山を、子供は大へんよろこんだ。あれは何、これは何と、母親からおもしろい物を見せてもらえるほかに、いろいろのおもしろい物を聞かしてもらうことができたからである。爪先あがりの細い径(こみち)が、藪や森の中を抜けて、だらだらとのぼっていく。ときには、草の生えた斜面を通ったり、そうかと思うと、おもしろい形をした岩の根かたを回ってゆくこともある。そうして、そこにはさまざなの物語をしべの奥にひそめた花だの、木精(こだま)を宿した大きな木だのがあった。山鳩がクルー、クルーと鳴いているかと思うと、土鳩がオワォ、オワォと悲しそうな声で鳴いていたり、蝉が、ミンミン、ジージー、カナカナ鳴いていたりした。
(略)
こうした参詣の日に、おとよと子供が家に帰りつくのは、いつもたいてい、夕闇が静かにあたりを立ちこめる頃であった。道のりもかなりあったし、それに往きも帰りも、町をかこむ渺々(びょうびょう)とした水田を小舟で渡らなければならなかったので、ずいぶんお練りの道中であった。そんなわけで、どうかすると帰りみちには、星かげや蛍火がふたりを照らすこともあったし、ときには月さえのぼることがあったりした。そんなとき、おとよはいつもしずかな声で、お月さまを歌った出雲の国のわらべ歌を、子供にうたって聞かせるのだった。
ののさん(あるいは、お月さん)いくつ
十三 ここのつ
それはまだ 若いよ
わかいも 道理
赤い色の 帯と
白い色の 帯と
腰にしゃんと 結んで
馬にやる いやいや
牛にやる いやいや
すると、あたりがとっぷりと水いろの夜に暮れきるまで、幾里も幾里も果てしなくつづく、一面の水田から、しずかに泡立つような蛙の合唱がわきおこってくる。まるでそれは、大地の底からわきおこるような一大合唱であった。おとよは、蛙のことばを、いつも子供に言ってきかせるのだった。――「ほらね、メカユイ、メカユイ。――目がかゆいよ、ねむくなったよって、蛙が鳴いてるだろ。」
そうして、こうしているうちは、なにもかもがほんとに楽しい時であった。
やがて、そうこうしているうちに、わずか三日のあいだに、永遠の神秘に属する生と死とをつかさどる神の摂理が、つづけざまに二度までも、おとよの心を打ちのめしたのである。まず最初に、おとよは、自分があんなにいくどとなく無事を祈ったやさしい夫が、とうとう不帰の客となった――この世の借りものである一切の形骸から、もとの塵にかえってしまったことを知らされたのである。それからまもない二度目の時には、おとよは、自分の子供が、漢方医の手でも醒ますことのできない、深い眠りについたことを知らされたのである。おとよがこれらの出来事をさとったのは、一閃(いっせん)、キラリとひらめく稲妻の光の中で、物の形をパッとさとったのと同じであった。そして、この二つの稲妻の閃(ひらめ)きと閃きの間も、それからその先も、ともにいっさいは神の慈悲なる絶対無明の闇であった。
やがて、その闇もいつとなしに去ってしまうと、ようやくのことで起き上がったおとよは、こんどは、「おもいで」という百年の仇敵に行きあった。この仇敵以外のものの前では、おとよは、あいかわらず依然と同じように、いつもにこやかな、愛くるしい顔をしていられたのである。けれども、この「おもいで」という客と差し向かいになると、おとよは、つくづく自分の無力を感じた。おとよは、よく畳の上に小さなおもちゃを並べてみたり、小さな着物を広げてみたりして、じっとそれを打ち眺めては、小声でなにか話しかけたり、物も言わずにひとりでにたにた笑ったりした。けれども、その微笑は、いつもかならずその果ては、激しいむせび泣きに終わるのが常だった。そうして、畳に頭をすりつけては、たわいもない問いを神仏にかけるのが癖のようになった。
(略)
こうして、春は去り秋は来たり、いくどかの季節が去っては来たりして、やがておとよの父親は、娘にもういちど婿を迎えてやろうと思い立った。そして、母親にいった。
「うちの娘にも、あれでもういちどせがれでもできたら、あれにとっても大きな喜び、わしらにとっても大喜びだがのう。」
ところが、物のわかった母親は、それに答えていった。――
「あの娘は、けっこうあれでしあわせでいますよ。再縁するなんて、とてもあの娘には思いもよりません。この節じゃ、すっかりもう、苦労も罪もなんにも知らない、ほんのねんねえになってしまいましたもの。」
おとよが、真の心の痛みを覚えぬようになったことは、事実だった。ところが、だいぶ前からおとよは、どんな品にかぎらず、きわめて小さなものに、ふしぎな嗜好を見せはじめていた。最初はまず、自分のふだん寝起きする蒲団が、どうもこれでは大きすぎると言いだしたのである。おそらくこれは、添い寝する子を亡くしたあとの、空虚な感じからいうのであったろうが、そのうちに、だんだん日がたつにつれて、他の品でも、何によらず大きすぎるように思われてきだしたのである。げんに、住んでいる家からしてがそれで、長年住みなれた座敷やら、見慣れた床の間やら、床の間にある大きな花瓶やら、――しまいには、日常つかう膳椀のような什器までが、大きすぎるように思われてきた。飯をたべるにも、おとよは子供の用いるような、ごくちいぽけな椀から、お雛さまのような箸で食べたがった。
こうしたことにも、おとよは、家では親たちから慈愛ふかく、なにごとも気まかせにされていた。そうして、ほかのことにはかくべつ変った選り好みはなかったのである。そんなわけで、年とった親たちは、暇さえあれば、しじゅう娘のことで、折につけては談合した。とうとうしまいに、父親がこんなことを言いだした。
「うちのおとよも、あの分じゃ、いまさら見ず知らずの赤の他人といっしょに暮らすのも辛かろう。といって、わたしたちももう寄る年なみだ。おっつけ、あれを跡にのこしてゆくことは知れている。まあ、あれひとりで身すぎとでもいうことになれば、まず尼さんにでもするよりほかに、道はあるまいぞ。どうだな、ひとつあれのために、小さな堂でも建ててやることにしては。」
そのあくる日、母親は、おとよに尋ねてみた。――
「おまえね、尼さんになるのは、おいやかい? 尼さんになって、小さな須弥檀(しゅみだん)だの、小さなご本尊さまをお供えしてさ、ごくもうちんまりとしたお堂で、おまえ、暮らす気はないかい? お父っあんやおっ母さんも、しじゅうそばにいてあげるんだよ。おまえがもしその気がおありなら、お坊さんにお願いして、おまえにお経をおしえていただくようにするけどねえ。」
おとよは、それを希望した。そして、ごく小さな尼の法衣を一枚こしらえてくれ、といって頼んだ。けれども、母親はいった。――
「そりゃおまえ、ほかの物なら、なんでも小さくしてこしらえて上げられるけれど、法衣だけはだめだよ。尼さんというものはね、大きな法衣を着なければいけないものなんだよ。お釈迦さまが、そうおきめになったんだからね。」
そういわれて、おとよはようやくのことで、よその尼さんたちと同じ法衣を着ることを承知したのである。
やがて、両親はおとよのために、むかしあみだ寺という大きな寺のあった境内に、一宇の小さな庵寺を建立した。そして、この庵寺も、おなじようにあみだ寺と呼び、名のごとく、あみだ如来を本尊に安置し、ほかの諸仏も勧進した。堂には、ごく小さな須弥檀に、おもちゃのような仏具をそなえた。ちいさな経机に、ちいさな経本、小さな衝立、ちいさな鐘、小さな掛け物などが、そこに並べられた。そして、おとよは、両親のみかまったのちも、この庵寺でながく暮らした。ところの人たちは、おとよのことを、あみだ寺の比丘尼と呼んだ。
おとよは、毎日、朝の托鉢(たくはつ)をすませてしまうと、小さな機台の前に坐るのがならわしであった。けれども、おとよの織る手織りの布は、とても満足な用には立たないような、織り幅の狭いものであった。それでも、おとよが織った手織り地は、彼女の身の上を知っている幾軒かの商店主が、きまって買いとって行った。そういう商店主たちは、おとよに、ごく小さな茶わんだの、小さな花瓶だの、庭におく枝ぶりの変った盆栽などを贈り物にした。
このおとよが、一ばんおおきな楽しみにしていたことは、子供たちと仲よしになることだった。それには、おとよはいつも事欠かなかった。いったい、日本の子供の生活というものは、たいていはお寺の境内で過ごされるもので、このあみだ寺の境内でも、ずいぶん多くの楽しい幼少年時代が過ごされたものである。おなじ町内の母親たちは、みんなこの寺の境内で、自分たちの子供を遊ばせることを好んだ。そのかわり、比丘尼さんのことを決して馬鹿にしてはいけないよと、子供たちにくれぐれもよく注意してやった。母親たちは、よく言い言いした。「どうかするとね、妙なまねをなさるようなことがあるかもしれないけれど、それは前に一度、あの比丘尼さんは、ご自分にかわいい坊ちゃんがおありになったのを、お亡くしになったもんだから、その辛さが、お母さんとして胸いっぱいにおありになるんだからね。だから、おまえたちも、比丘尼さんには、ようくおとなしくして、失礼のないようにしなくちゃいけないよ。」
子供たちは、みなおとなしかったけれども、相手を敬うという意味では、あんまり礼を欠かない方だとはいえなかった。固苦しい行儀を守るよりも、子供たちは、万事よろしきようにやることをこころえていた。それでもかんしんに、おとよのことを「比丘尼さん、比丘尼さん」と呼んでは、ていねいにお辞儀だけはするのだが、それはその時こっきりで、そうでない時は、自分たちと同じ仲間並みにあつかった。そして、一緒に仲間に入れては、いろんな遊びをするのだったが、おとよの方では、子供たちに小さな茶わんでお茶を出したり、豆粒ぐらいな餅を山とこしらえてやったり、そうかと思うと、子供たちの人形の着物に、木綿や絹の布地を、わざわざ織ってやったりした。そんなわけで、おとよは子供たちにとって、肉親の姉のようになった。
ところで、そうやって毎日のように、おとよと一緒に遊んでいた子供たちも、いつのまにか、おとよと昔のように遊ぶには、もうすっかり成人した大人になってしまい、あみだ寺の境内を去って、それぞれ世の中の辛い仕事にたずさわるようになり、やがて父となり母となって、こんどは自分たちの子供を代りに遊びによこすようになった。そして、そういう子供たちも、親たちがしたと同じように、みんな比丘尼さんのことを好くようになった。こんなふうにして、あみだ寺の比丘尼は、このお寺が建てられた時分のことをおぼえている人たちの、子供や、孫や、曾孫たちといっしょに遊ぶまで、長生きをしたのである。
近所の人たちも、おとよが不自由な思いをしないようにと、何かにつけてよく目をかけてくれた。そんなわけで、おとよのところには、いつでもおとよが自分一人で事足りる以上の、余分な喜捨があった。したがって、おとよはそれらの子供たちに、なんとか思うままの親切をつくしてやることができたし、犬・猫のような動物などにも、ありあまるほどの餌をやることができた。小鳥たちは、お堂の中に巣をつくって、おとよの手から餌をついばんだ。おとよは、そういう小鳥たちに、仏さまの頭などに止まってはいけませんよ、といって教えた。
おとよの葬式がすんでから、幾日か経った後のことである。ある日、わたくしの家へ大ぜいの子供たちが、打ちそろって訪ねてきた。九つばかりの女の子が、みんなに代って、次のように述べた。
「おじさん、わたいたち、お亡くなりになった比丘尼さんのことで、お願いがあってきたんやで。比丘尼さんのお墓に、大へん大きなお石塔が立ったの。とても立派なお墓やわ。でも、わたいたちも、みんなして、ごく小さな小さなお墓をひとつ立ててあげたいと思うんです。比丘尼さんがまだ生きてござった時分に、お墓ならごく小さなお墓が好きやて、よくいうてござったでね。で、石屋さんに聞いたら、お金さえ出せばこしらえたる、いいのをこしらえたる、いうんです。そげすて、おじさん、おじさんもいくらか出してごすなさいな。」
「ああ、出しますとも」とわたくしは言った。「でも、あんたがた、これから、遊ぶところがなくなってしまったでしょう。」
すると、女の子は、にこにこ笑いながら、答えた。
「いいえ、わたいたち、やっぱりあみだ寺の御境内で遊ぶわ。比丘尼さんは、あすこに埋められてござるでね。きっと、わたくしたちの遊んでいるのを聞いて、喜んでごしなさるわ」
 ずっと前から載せたいと思っていた、私がとても心をつき動かされたエピソード。何度か紹介していますが、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の『東の国から・心』(恒文社)より(詳しくは右画像クリック)。
ずっと前から載せたいと思っていた、私がとても心をつき動かされたエピソード。何度か紹介していますが、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の『東の国から・心』(恒文社)より(詳しくは右画像クリック)。
昔は独身となった女性は出家して尼になる人も多かったわけですが、今はその選択肢さえ難しくなりました。こんな時代でも、実際に尼になれたような人はある意味、恵まれてるように思えます。
—————————————————————————–
◆この上なく高貴だった日本女性 ~ 明治の武士
◆“男の浮気” と “子供の死” には覚悟をしておいた方がいい ~ 本当に強い女性とはこういうこと。女としてのポジション確認
◆武士の子女教育カリキュラム ~ 貝原益軒『和俗童子訓』より
◆子育て、死生観が変わる。読んでおきたい日本の古典 ~ 『土佐日記』と、一茶の俳句
◆失われた日本人の精神性と天皇の祈り① ~ 信仰とは信条を持つこと。神を信じる否かは関係ない ~ 母と子が父の無事を祈る『里の秋』
◆「イケメン」なんて言葉は朝鮮語! 日本語にそんな言葉ありません!~ 貧脳になる、マスコミが流行らせた使ってはいけない言葉
◆ヘナチョコ男とパッパラパー女はいらない ~ 命とは尊く儚いもの
◆映画『Sayonara』 愛を貫いて死を恐れない、ヤマトナデシコ~ 変れば変るもの。日本人の美意識
◆幼い子には、やっぱりお母さんの子守歌を毎晩、聴かせてあげましょうね!
◆失われた日本人の精神性と天皇の祈り③ ~ 日本人の精神性は世界随一であった
◆フランス革命ネタです。“暗殺の天使”シャルロット・コルデーと「マラーの死」
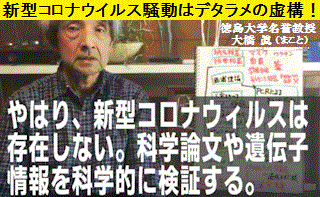



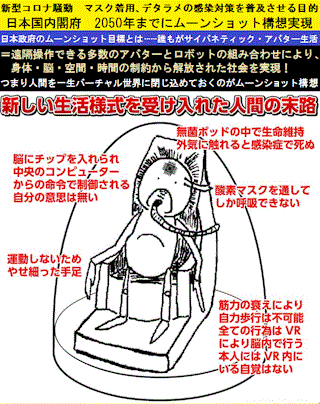
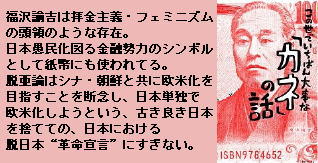


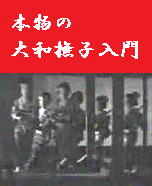


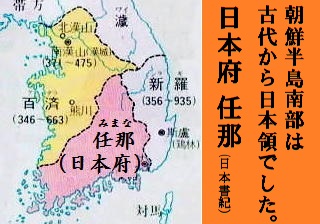

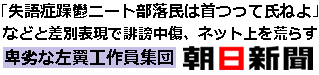













































この記事に対するコメント
このような女性は本当にいたでしょうね。
ひとりひとりが逃れられない運命というものを背負って生きていると思います。
人生の上り坂がキツいこともしばしばですが、頑張っていこうと思えました。
長い文章を転載私ご紹介くださり、どうもありがとうございます。
最近、自分に子供がいなければ世の中と闘うこともなかったし、行政に反抗することもなかったし、周りから悪目立ちすることもなかったろうなあ・・・と思うことがあります。あくまで「私は」の話ですが、日本の未来も真実の歴史も学校教育もどうでも良かったでしょうし、食べ物やら何やらそこまで気にすることもなかったでしょうし、全員がマスクをしている所では自分も何の疑いもなくマスクをしたでしょう・・・
そんな折、幼い時のことをふと思い出しました。
母が私を膝に乗せながら真顔で「お母さんまだ27歳なんだよ。子供がいなければ、まだお姉さんって呼ばれるトシなんだよ」と私の目を見て語りかけてきたのです。
私は、突然なに?と心の中で驚きつつ、見た目にはとてもお姉さんには見えないけどなぁ・・・と心の中で困惑したのを覚えています。
まさか私がそのことを覚えているとは母は思いもしないでしょう。母はもしかしたらその直前に誰かに「おばさん」とでも呼ばれてショックを受けていたのかもしれません。想像ですが。(昔はどんなに若くても子供が生まれたら「おばさん」と呼ばれていたみたいですね。今は「○○ちゃんママ」ですが・・・)
世間体を気にして、行政の指示通りに育てていけば、今この瞬間の私の苦労は無くなるでしょう。その代わり、別の苦労や悩みがやってくると思っています。(例えば母が経験したような)
私の今の苦労は、私の子供や孫やその先の世代への私からの贈り物と思っています。私は、丈夫な子供を何人も産む丈夫な日本人を未来に残したいです。
そう思ったら、今の苦労を取ることに迷いはありません。
いつか、私自身が死んだ後の時代に、ロデムさんのご子孫やここの読者様たちのご子孫と、私の子孫が、知らず知らずのうちに出逢うことがあるかもしれません。時空を超えてお互いの運命が交差したようで、面白いなあと想像します。
例え大昔に子育てするとしても、今度は野生動物の脅威に晒されるなど、やっぱり苦労はあると思うんです。子育てのみならず、人生に苦労はつきものですね。どの種類の苦労を選ぶか、それは個人の価値観次第です。
今ではもう、私は相手が行政職員であっても失礼な言動をしてきたら叱り飛ばして追い返せるようになりました。尻尾を巻いて逃げていきます。
本当の私は争いや諍いを好まないし、ヤクザみたいなことするのは嫌なんですが・・・
花嫁衣装は死装束だそうです。そしたら花嫁の化粧は死化粧でしょう。
娘時代の自分は死んだと思って、割り切っています。
ただ、子供だけは、子供時代だけでもなんの心配事もなくのびのび育ってほしいと願っています。
とてつもなく崇高で高貴な精神を持っていた大和撫子
日本女性。子育てほど素晴らしい行いはありませんね…
献身性と無性の愛こそが人類をルサンチマンから救う。